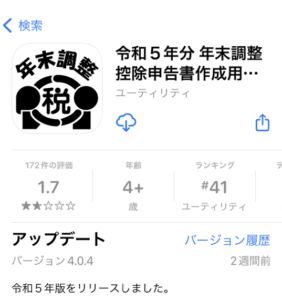会社設立時の役員報酬、ゆっくり決めても大丈夫??
支給開始時の注意点を解説

設立時は気持ちも⤴⤴・・・
法人の設立にはやることがいっぱい・・・でも
初めての法人設立
事業計画はもちろんのこと、法人の名称や資金の調達方法など
決めることはいっぱい。
税務署をはじめとする、役所に提出する書類も盛りだくさんで
特に特例を受けられる青色申告の承認申請は忘れずに出しておきたいです。
設立時の色んな手続きに追われ、忘れがちなのは役員報酬です。
事業が軌道にのってから決めようかなぁと漠然と後回しにしていると、
設立期の役員報酬を経費に計上できなくなる恐れもあります。
役員報酬は定期同額給与とすべし
役員報酬は利益操作の排除の観点から
法人税法上、期中は毎月同額で支給しなければなりません。
期末付近になって、利益が出そうだから役員報酬を急に増額したり、
逆に損失が出ないように役員報酬を減額した・・・
なんてことが出来ないように役員に対する報酬には
厳しい規定があります。
事業年度開始のから3か月以内に決定
役員報酬は、株式会社であれば「株主総会」で金額を決める必要があります。
株主総会を事業年度開始の日から3ヶ月以内に開催し
その事業年度の役員報酬を決定します。
開催した日以後は株主総会で決定した役員報酬が支給され
以後、事業年度終了の日まで毎月同額の役員報酬を支給しないと、
役員報酬額は法人税法上の経費(損金)に算入できません。
ちなみに翌期の株主総会決議まで、同額で支給する必要があります。
この規定は設立期も同様で、特段特例はありません。
例えば3月決算の法人が4月10日に設立したとします。
その場合、株主総会を3ヶ月以内の7月10日までに開催し、
遅くとも8月支給分から役員報酬を支給する必要があります。
役員は賞与を出せない?事前確定届出給与の活用
役員でも賞与を支給することができます。
ですが、この賞与も定期同額給与同様に、厳しい規定があります。
次に記載する日のいずれか早い日までに「事前確定届出給与に関する届出書」
を税務署へ提出すると役員賞与を支給することが出来ます。
①株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日
②会計期間開始の日から4か月を経過する日
「事前確定届出給与に関する届出書」には未来の支給日と支給金額を記載しますが、
必ず、その支給日と支給金額を守る必要があります。
もし、100万円支給すると記載したのに50万円しか支払わなかったった場合、
その支給した50万円は経費から除外されます。(所得が増えてしまいます・・・)
今期は利益が出そうだなと予測できる時は、この「事前確定届出給与」を
活用してはいかがでしょうか。
登記されていなくても役員?みなし役員に注意
役員でもう一つ注意しないといけないのが「みなし役員」です。
役員とは会社の謄本に記載がある「代表取締役」「取締役」「監査役」
だけではなく、法人税法上の「みなし役員」もあります。
「みなし役員」にも定期同額給与や事前確定届出給与の縛りがあるので
注意が必要です。
では「みなし役員」とはどのような役員をさすのでしょうか。
みなし役員の定義
みなし役員は次のいずれかに該当する人いいます。
①法人の従業員以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
「経営に従事」とは一般に、その法人の重要な業務執行の意思決定に参加しいることを意味します。
②同族会社の従業人のうち、株式の所有割合が一定以上で、その法人の経営に従事しているもの
株式の所有割合は以下の要件となります。
・その従業員が所属する株主グループの所有割合が10%を超えている
・その従業員と配偶者等の親族の株式の所有割合が5%を超えている
代表取締役の配偶者の方が「みなし役員」に該当する場合が多く、
働き方は従業員さんと同じだけれど、経営に従事するかどうかや
株主の所有割合要件の確認が大切です。
まとめ
法人を設立する際は、新たに行う事業の事で頭がいっぱいになると思います。
ですので、税金周りの事までなかなか手が回らないのが実情です。
そのようなときは是非専門家を活用するのがおすすめです。
ご自身は事業活動に邁進し、事務周りや手続き周りで外注できるものしちゃうのもアリですね。